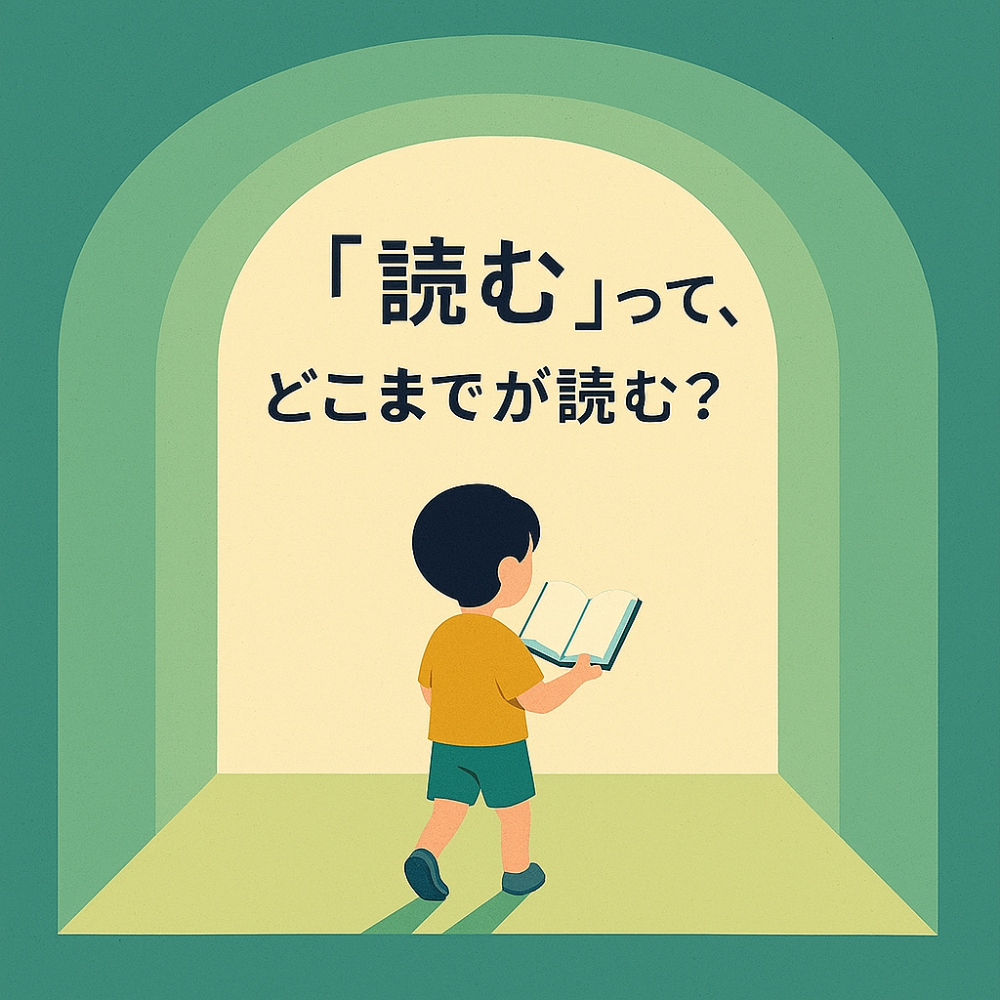“読む”という行為は、まるでトンネルに入るようなものです。
文字を追うことは入口にすぎません。その先には理解や想像の広がりがあり、出口は一つではなく、子どもによって違う光の場所にたどり着きます。ある子は物語の感情に共感して出口に出るかもしれませんし、ある子は論理を追って別の出口に出るかもしれません。ときには途中で立ち止まり、「ここで考えたい」と思うこともあるでしょう。
では、“読む”とはどこまでを指すのでしょうか。
1. 入口:文字を追う
まずは文字を目で追うこと。声に出して読む、黙って読む。ここがトンネルの入り口です。
2. 理解:意味をつかむ
次に、物語の筋を追えたり、説明文の要点を理解できたりする段階。ここで多くの子どもは「読めた」と感じます。
3. 考える・感じる:問いを持つ
さらに進むと、「なぜ?」「どうして?」と考えたり、登場人物に共感したりする場面が出てきます。読むことが自分の中に響き始める瞬間です。
4. 対話する:自分の言葉にする
最後に、書き手の意図を想像したり、自分の経験と結びつけたりする段階。読むことが単なる理解を超えて、学びや生き方に広がっていきます。
読むことは単なるスキルではなく、奥行きのある探検です。
子どもがどの段階にいるかを見守り、問いや会話を通じて「次の出口」へ導いてあげることが、親や教師にできる大切なサポートなのだと思います。